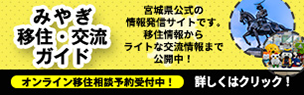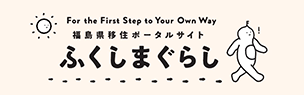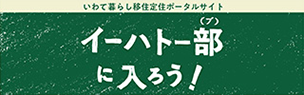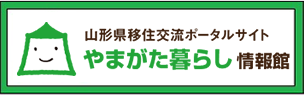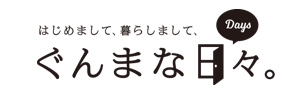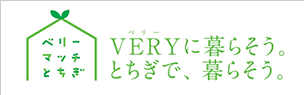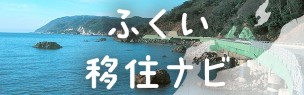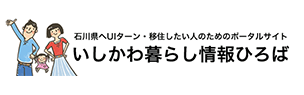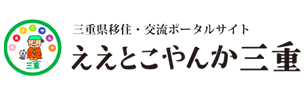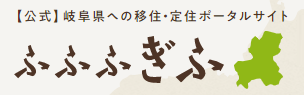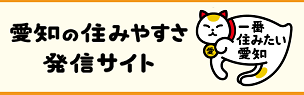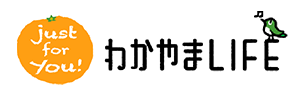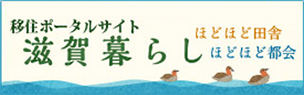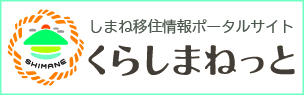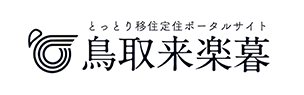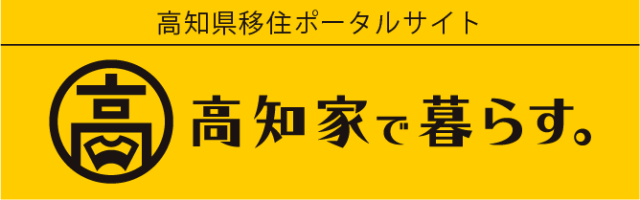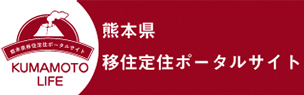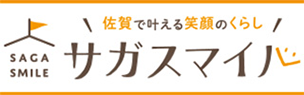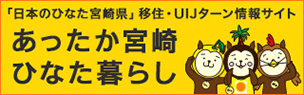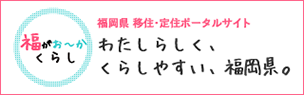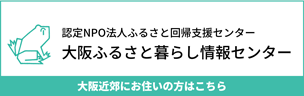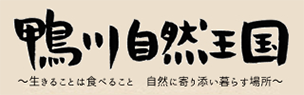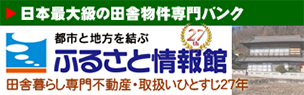VIEW MORE
VIEW MORE
2024.07.19
長野県、東北6県フェア、過去最高の集客
群馬県議会議員 7月も半ばを過ぎ、やっと梅雨が明け、夏の太陽がアスファルトの舗道を照り付けている。近年はこの時期になると九州など西日本が豪雨に見舞われているようで、温暖化の影響などもあるのかと気になっている。心からのお見舞いを申し上げます。 7月は、夏休みに移住希望地を訪れる計画を立てる人も多く、市町村主催移住セミナーや各県フェアが多くなる時期だ。13日に開催された長野県の「信州で暮らす、働くフェア」は472組731名の移住希望者が押しかけ、大盛況となった。長野県は2011年から2019年まで(14年と16年除く)、移住希望地ランキングでトップに立つなど、県内各自治体の受け入れ態勢が確立している。しかし、2020年に新型コロナウイルスが日本を襲い、東京圏を取り巻く各県が人気となりトップの座を静岡県に譲り現在に至っている。こうした中で初めて、センターの事業部がこのフェア開催を請け負った。長野県の集客の多さに、センター内では「やはり長野はすごい集客力だ」と話題になっている。今回は県内77自治体の内45自治体が参加。企業も30社、県内各団体25団体の計100団体が集まって、このフェアを盛り上げた。参加者の世代は30~50代で77.1%、男女比は女性が48.5%、男性が49.8%。「フェアの開催を何を見て知ったか」については、SNSが19.3%、移住ポータルサイトが16.9%、回帰支援センターHPが15.9%などとなった。参加者の傾向も明らかになり、次につながる成果となった。 7月6日に開催された7回目の「東北移住&つながり 大相談会2024」は東北6県から117自治体、121ブースが開設され、東京交通会館12階で行われた。各県からは、青森が14、岩手が19、宮城が15、秋田が13、山形が17、福島が39の計117自治体が参加。参加者は過去最高の前年比125%増の410名と賑わった。参加者も従来はUターン希望の一人での参加者が多かったが、今年はキッズコーナーを設置したこともあってか、家族連れの本気度の高い参加者が目についた。東北地方は人口減が他県に比べ進んでいるといわれるが、センターとしては、それぞれの県や自治体が工夫を凝らし、しっかり受け皿を整備して確実に移住者を増やしてきていると評価している。 戦後80年、地方から東京への人の流れをつくり、戦後の繁栄を勝ち取った日本。同じ年月をかけて、東京から地方への人の流れ(ふるさと回帰運動)をつくり、国としての活力を取り戻すしかないと思っている。勝負はまだまだついてはいない。最近、2014年からの地方創生は失敗だったなど軽々に評価する人が一部にいるが、10年くらいで結果が出るほど簡単なことではないと22年間取り組んできて思う。地方創生はこれからが本番だ。 取材・来客は、16日は岐阜県議会判治議員、多治見市議会議員3名、中津川市議2名、恵那市議会議員1名が視察。17日は山越地方災害補償基金理事長着任挨拶、宮城県女川町副町長視察、東京都清水都議、檜原村議2名、奥多摩町議1名が視察。19日は岐阜県山県市議5名視察、宮崎県西米良村の黒木村長と五ヶ瀬町担当者来訪、群馬県議団18名視察。